�@
 �@�@�@�@
�@�@�@�@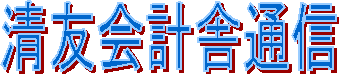
��P�P���i2005�N4���j
����17�N�x�̐Ő����������\����܂����B�Љ�̏��q����A�I�g�ٗp���x�̗h�炬�⓭�����̉��l�ς̑��l���A���ƍ����̐[�����Ȃnj��ς���Љ�f�����Ő������ƂȂ�܂����B
���܂ł́A�藦���ŁA�V�N�ҍT���ȂLj��̗v���ɂ͂܂�ΒN���������Ɍ��ł����鎞��ł����B
�������A���N�̉����́A��w�̊�Ɠw�͂�����Ό��ł����鎞��ɕω�����Ǝ���������e�ł��B
![]()
|
�l�ޓ����i����P���j���i�Ő��̑n�� |
|
���̔N�̋���P������O2�N�Ԃ̋���P����̕��ϊz��葝�������ꍇ�A�@�l�łƖ@�l�Z���ł̐Ŋz�T�������܂��B |
![]() ��̗��@�@�i�ڂ����v�Z���@�͗��ʂ��������������j
��̗��@�@�i�ڂ����v�Z���@�͗��ʂ��������������j
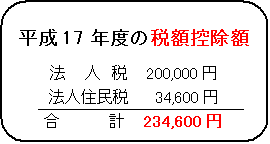
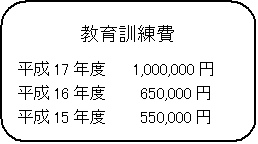

![]() ����P����Ƃ́E�E�E�H
����P����Ƃ́E�E�E�H
�@�]�ƈ��i�����͑ΏۊO�j�́u�m���A�Z�\�E�Z�p�̎擾�v�܂��́u�Ƌ��⎑�i�̎擾�v��ړI�Ƃ������
|
�P |
�u�t�E�w�������o�� |
�ЊO�u�t�A�w�����Ɏx�����u�t���A�w������ |
|
�Q |
���ޔ� |
���C�p�̋��ށA�v���O�����̍w�����Ȃ� |
|
�R |
�O���{�ݎg�p�� |
���C���s�Ȃ����߂Ɏg�p����O���{�݂̗��p���Ȃ� |
|
�S |
���C�Q���� |
��ƌo�c�̊ϓ_�����Ƃ��]�ƈ��̋���P����K�v�Ȃ��̂Ƃ��Ďw�肵���u�����̎�u��p�A�Q����p |
|
�T |
���C�ϑ��� |
�u�t�A���ޓ����܂ߌ��C�S�̂��O������@�ւֈϑ�����ꍇ�̔�p |
![]() �K�p�����@����17�N4��1���Ȍ�J�n���ƔN�x�`�R�N��
�K�p�����@����17�N4��1���Ȍ�J�n���ƔN�x�`�R�N��
![]() �@�K�p�̃R�c
�@�K�p�̃R�c
�@�̔���E��ʊǗ���Ɂu����P����v�����݂��܂��傤�B
�܂��A�ߋ�2�N�Ԃɍs�Ȃ�������P����̂����Ŋz�T���̑ΏۂƂȂ���̂��E���o���K�v������܂��B
����̐Ŗ������ɔ�����Ӗ��ł��A�E���o��������P����̐��������̃R�s�[���Ƃ�ꊇ���ăt�@�C������ȂǍH�v���K�v�ł��B
![]() �@����ΏۂƂȂ�P����A�ΏۂƂȂ�Ȃ��P����̋�̗Ⴊ���炩�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@����ΏۂƂȂ�P����A�ΏۂƂȂ�Ȃ��P����̋�̗Ⴊ���炩�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�ڍׂ�����������A���ЂɂăZ�~�i�[���J�Â���\��ł��B
|
������ƐV���Ɗ������i�@�ɂ��Ő��x���� |
|
������ƐV���Ɗ������i�@�̏��F�����ꍇ�ɂ́A�@�@�ݔ������ɑ�����ʏ��p��Ŋz�T���@�A�@���F���Ԓ��͗��ۋ��ېł�K�p���Ȃ��ȂǐŖ���̃����b�g������܂��B |
������ƐV���Ɗ������i�@�Ƃ́A�u�o�c�v�V�v�u�n�Ɓv�u�V�A�g�v�Ɏ��g�ޒ�����Ƃ̌o�c�v�V���قڑS�Ǝ�ɂ킽��A���L���x������ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���̂ŁA���u������ƌo�c�v�V�x���@�v���p�����̂ł��B
![]()
![]() �@
�@
![]() ��̗��@( ���e����Z����ɂ��ϓ����܂��@����17�N4�����_ )
��̗��@( ���e����Z����ɂ��ϓ����܂��@����17�N4�����_ )
|
���x�� |
���Z�@�� |
�ݕt���x�z |
�ݕt���� |
�ݕt���� |
|
������ƌo�c�v�V���x���ݕt |
������Ƌ��Z���� ���H�g���������� |
�ݔ����� �@7.2���~ �������^�]�����@2.5���~ |
0.7�� �`1.75�� �@�@�� |
�ݔ�����
15�N�`20�N �i���u�Q�N�j �^�]����
5�N�`7�N �i���u1�`3�N�j |
|
�����������Z���� |
�ݔ������@7200���~ �� �^�]�����@4800���~ |
1.55�� �@�@�� |
||
|
�V���Ƒ��i�x�� �����Z�� |
�n�����s �M�p����,�M�p�g�� ���H�g���������� |
�ݔ������@ �@�@ �P���~ �^�]�����@ 3500���~ |
1.7�� �ۏؗ� 0.7�� |
�ݔ����� �@�@�@�@10�N �@�@�@�@�@�i���u�R�N�j �^�]���� �@�@ �@�@5�N �@�@�@�@�@�i���u1�N�j |
�y���K�͊�Ǝғ��ݔ����������̓���z
���̑������q�ň��z�܂Ŏؓ��ł��鐧�x������܂��B�i���x��l�X�Ȑ�����܂����c�j
���ݕt����ۂɂ͌o�c�v�V�v��̏��F���鑼�ɋ��Z�@�ւ̋��Z�R�����邱�Ƃ��K�v�ł��B
![]() �o�c�v�V�v��̏��F����ɂ́E�E�E�H
�o�c�v�V�v��̏��F����ɂ́E�E�E�H
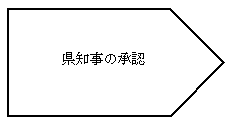
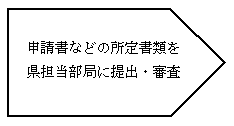
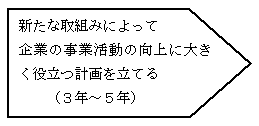
�@![]() �@���F�̏����@���̂����ꂩ�����v��𗧂Ă�K�v������܂��B
�@���F�̏����@���̂����ꂩ�����v��𗧂Ă�K�v������܂��B
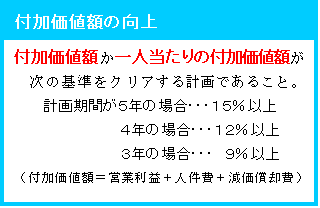
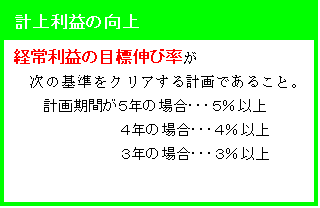
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���́@
![]() ���Ђɂ����F�\���̎x���Ɩ��������Ȃ��Ă���܂��B���ЁA�����k���������B
���Ђɂ����F�\���̎x���Ɩ��������Ȃ��Ă���܂��B���ЁA�����k���������B
�i���ʂɂÂ��j
|
���̑��̎�ȉ��� |
![]() �@�^���X���̓�������ւ̎����ĊJ
�@�^���X���̓�������ւ̎����ĊJ
������^���X�����������Ɏ����邱�Ƃ̂ł�����Ԃ�����17�N4��1���`����21�N5��31���܂łɍĊJ����܂����B
�������A�ĊJ��ɓ�������Ɏ����銔�ɂ��Ă��݂Ȃ��擾���z�i����13�N10��1���̊����̂W�O���j�͔p�~����܂����B
![]() �@�Ōy���[�u�̉���
�@�Ōy���[�u�̉���
�u�s���Y�����_�v��u���ݍH�������_�v�̌y���ŗ��̓K�p���A����19�N3��31���܂ʼn�������܂����B
![]() �@�藦���ł̏k��
�@�藦���ł̏k��
����18�N���ȍ~�̏����łɂ��Ē藦���ł���������܂��B
�����Ŋz��10�������z�i�����O20���j�A���125,000�~�i�����O250,000�~�j
![]() �@�t���[�^�[�ɑ���ېł̋���
�@�t���[�^�[�ɑ���ېł̋���
����18�N1��1���Ȍ�̑ސE�҂ɂ��Ă��A���^�̎x���z��30���~����l�ɂ��Ắu���^�x�����v�̒�o���`���t�����܂����B
�Q�l�@�F�@�l�ޓ����i����P���j���i�Ő��̌v�Z���@
�y�@�@�l���@�z
�@�@�����̋���P����������i���j��40��
�Ŋz�T���z����������P����̊z�~20��
�A�@�����̋���P�����������40��
�@�@�@�@�@�Ŋz�T���z����������P����̊z�~����P�����������~0.5
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@��������P����̊z �\ ���O2���̋���P����̕��ϊz
![]() �@�@���@����P��������� ��
�@�@���@����P��������� ��
�@ �@
���O2���̋���P����̕��ϊz
�������A�Ŋz�T���z�͓����̖@�l�Ŋz��10�������x�Ƃ���B
�@�y�@�@�l�Z���Ł@�z�@
�@�@�@�@�@�@�@�Ŋz�T���z���Ŋz�T���z�~17.3���i���s���Ł@�W���ŗ��j
�i���Ӂ@�ŗ��m�@�X���T�q�j�@�@